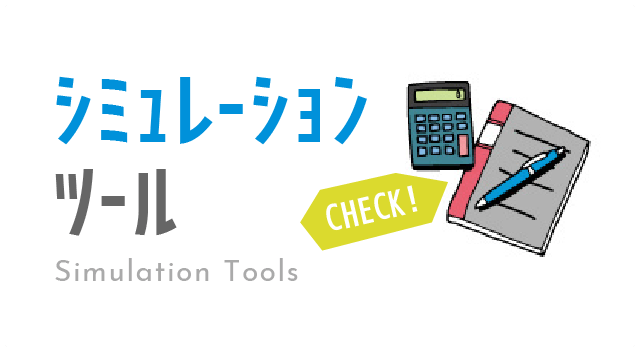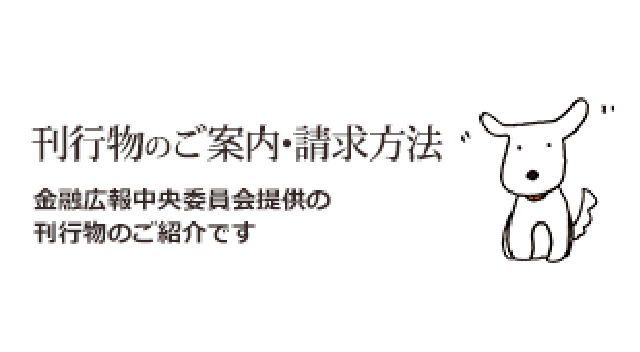⼤分県のみなさんに暮らしに役⽴つ
お⾦や金融・経済の情報をお届けします
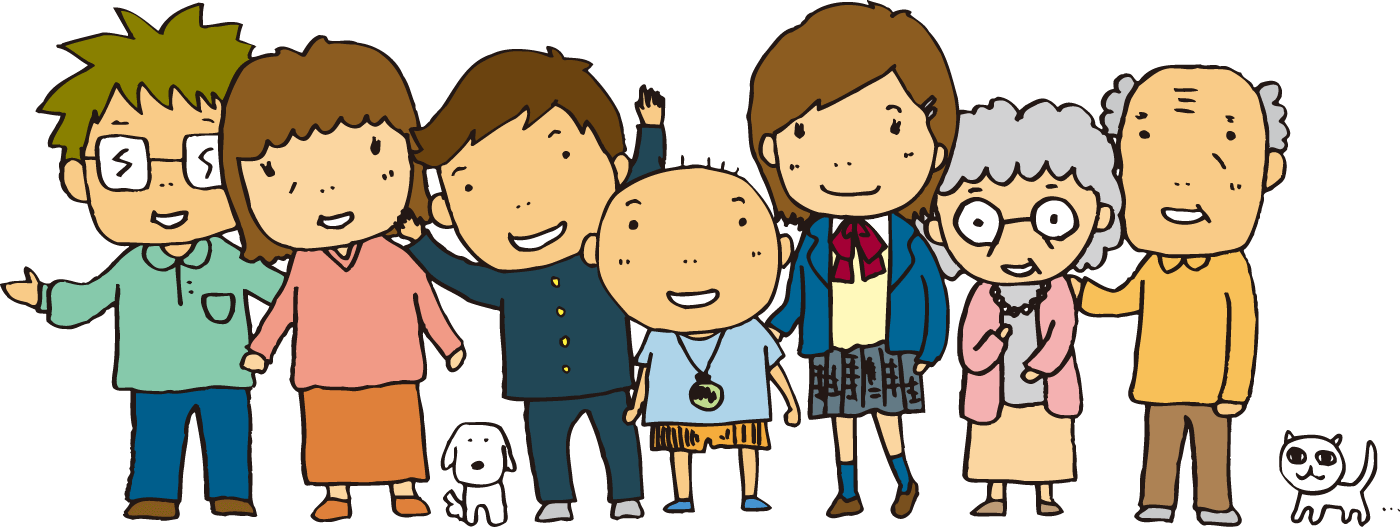
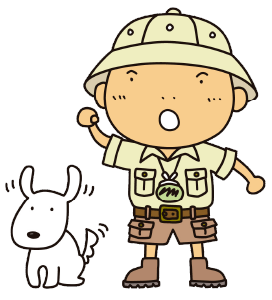
About us大分県金融広報委員会のご紹介
暮らしに役立つお金や金融・経済に関する情報を分かりやすく提供するための活動を行っています。

Lecturer dispatch講師派遣
講演会や勉強会、学校での授業、企業の内部研修などに講師(⾦融広報アドバイザー)を無料で派遣しています。